
小さい頃、母の後ろ姿を見ながら、
私はいつも「ていねいって、なんだろう」と思っていました。
味噌汁をすくう手つき、
野菜の皮をむく音、
お米を研ぐときの静かな水音。
どれもこれも、大げさじゃなく、
けれど確かに、心がこもっていて。
「ていねい」って、
誰かに見せるためじゃなく、自分の中にある“やさしさ”を形にすることなのかも。
そう思えるようになったのは、大人になってからでした。
手をかけること=時間をかけること、ではない
母は、時間をかける料理ばかりしていたわけではありません。
冷蔵庫にあるものでさっと作った炒めもの、
切って並べただけのトマト、
買ってきたお惣菜にちょっと薬味を添えたお皿。
それなのに、どうしてあんなに心が落ち着いたのだろうと、
今になって不思議に思います。
それはきっと、「ていねい」は“気持ちを向ける”ことだったから。
無理をせず、そのときの自分にできることを、
ちゃんと大事に扱っていたから、味にも空気にも、にじみ出ていたのだと思うのです。
きれいに整っていなくても、ていねいは生まれる
台所に立つたび、
完璧にできない日もあります。
ごはんがちょっと焦げたり、
切り方がバラバラだったり、
盛り付けがいまいち決まらなかったり。
でも、そんなときでも、
「これでいいよ」と自分に声をかけられるとき、
それこそが母が教えてくれた“ていねい”なのだと思います。
ていねいとは、整っていることじゃない。
心をこめること。
自分や誰かに、やさしくすること。
わたしに根づいた「ていねい」
母が大切にしていた菜箸、
布巾、土鍋。
ひとつずつ受け継いできたように、
私の中にも、あの“ていねい”は少しずつ根づいてきました。
今、私の作るごはんに、
母が宿していたようなやさしさが、
すこしでもにじんでいたらいいなと、そっと願いながら。
最後に
「ていねいでありたい」と思うとき、
私の心はいつも、台所に立つ母の後ろ姿を思い出します。
やさしく火を見つめるまなざし。
味噌をとく手のぬくもり。
それを静かに支えていた空間のあたたかさ。
ていねいとは、生き方の形。
そして、その形は、台所から静かに紡がれていくもの。
今日も、わたしの手の中から、
母のていねいが続いている――
そんな気がして、台所に立っています。
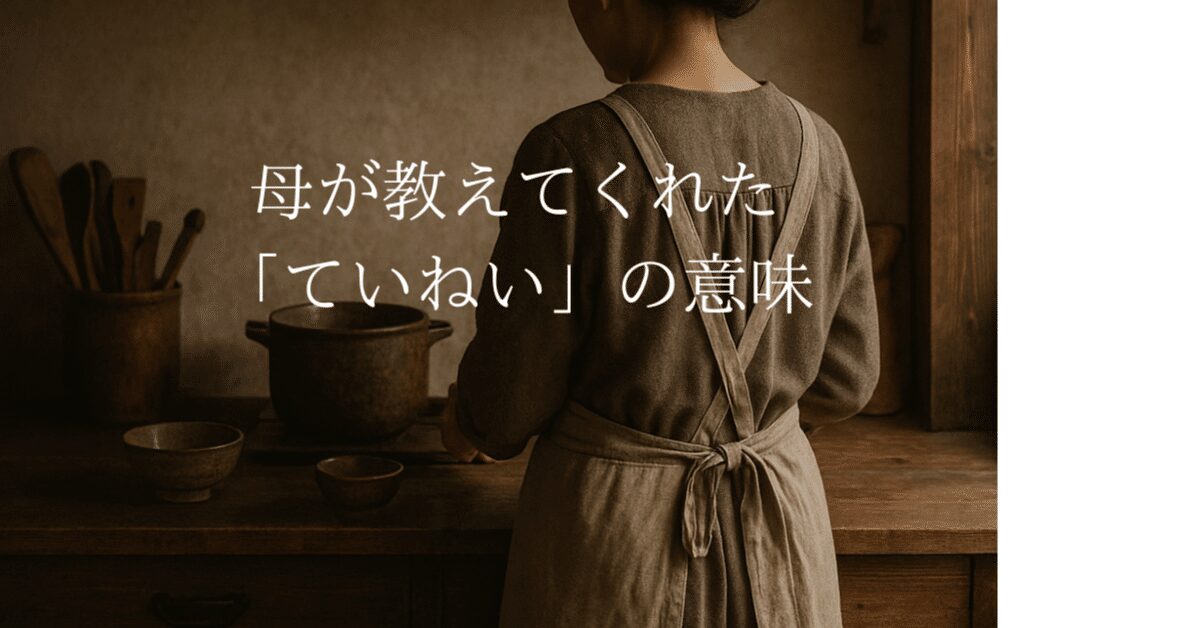


コメント